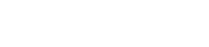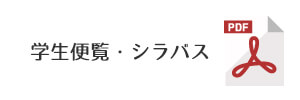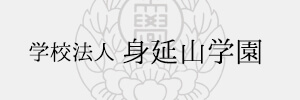- HOME
- 身延山大学仏教学会
身延山大学仏教学会
身延山大学仏教学会
身延山大学仏教学会は、平成7(1995)年4月の発足以来、本学の学長を会長に戴くとともに、専任教員を評議員・維持会員(この中から、会長が編集・会計・庶務の各種担当を委嘱)とし、本学OBや日蓮研究者・仏教研究者などを一般会員として構成されてきた学会です。学会の監事2名は、一般会員・維持会員の中から会長が委嘱しています。
| 宮崎英修 | (平成7〔1995〕年4月~平成8〔1996〕年3月) |
|---|---|
| 仲澤浩祐 | (平成8〔1996〕年4月~平成11〔1999〕年3月) |
| 浅井圓道 | (平成11〔1999〕年4月~平成14〔2002〕年3月) |
| 中條暁秀 | (平成14〔2002〕年4月~平成15〔2003〕年3月) |
| 宮川了篤 | (平成15〔2003〕年4月~平成22〔2010〕年3月) |
| 中山光勝 | (平成22〔2010〕年4月~平成22〔2010〕年11月) |
| 浜島典彦 | (平成22〔2010〕年12月~平成31〔2019〕年3月) |
| 望月真澄 | (平成31〔2019〕年4月〜令和2〔2020〕年3月) |
| 池上要靖 | (令和2〔2020〕年4月~令和4〔2022〕年3月) |
| 望月海慧 | (令和4〔2022〕年4月~現在に至る) |
身延論叢
身延山大学仏教学会の機関誌である『身延論叢』の前身は、祖山学院時代の大正2(1913)年10月に創刊号が発行された『棲神』です。『棲神』は戦中・戦後の混乱のなか昭和18(1943)年より昭和28(1953)年の間の中断はあったものの、身延山専門学校・身延山短期大学時代も発行が継続され、平成7(1995)年3月の第67号まで発行を重ねるに至りました。
平成7(1995)年4月、身延山短期大学は4年制の身延山大学へと改組転換を果たしました。それに伴って、『棲神』の発行母体である身延山短期大学学会も身延山大学仏教学会へと改組され、あわせて、その機関誌も『身延論叢』へと名称を改めました。平成8(1996)年3月に創刊号が出された『身延論叢』は、現在に至るまで刊行を継続しています。各号の収録内容は以下の通りです。
身延論叢一覧
| 【創刊号】 | |
|
創刊に際して 宮崎英修 創刊の辞 仲澤浩祐 望月海淑 「法華経における法の語の使用例─譬喩品から授学無学人記品まで─」 高橋堯昭 「樹神信仰の系譜─釈尊の風土・精神的基盤─」 町田是正 「法華経にみる実践としての智慧」 上田本昌 「日蓮聖人最晩年の曼荼羅について─弘安四・五年を中心として─」 桑名貫正 「『開目抄』に見られる実践上の一念三千義について─報恩と法華経行者の値難意識を通して─」 奥野本洋 「通師門入学禅院と身延衆徒」 間宮啓壬 「日蓮にみる女性の救済─「一念三千の成仏」─」 関戸堯海 「「雨ニモマケズ手帳」における仏教思想」 中山光勝 「明治四年・伊賀農民騒擾裁判関係資料(一)─明治法制史料断片(二)─」 |
リポジトリ |
| 【第2号】 | |
|
〈論 文〉 岩田諦靜 「『摩訶止観』第五上第七正修止観における心意識(一念三千)説について」 三輪是法 「ジェンダー論からみた日蓮の性差観」 桑名貫正 「身延山十二世円教院日意上人伝に関する二、三の問題について」 〈資料紹介〉 中山光勝 「明治初年の「自裁」規則補遺─明治法制史料断片(三)─」 〈シンポジウム〉 大学をとりまく社会環境と仏教教育 提言:大学に求められているもの 仲澤浩祐 大学の大衆化が進む中で、大学生をどのように育成するか 深山 正光 仏教教育の社会的役割(の根拠)をどのようなところに求めるのか 伊藤 瑞叡 大きく変動する社会の中で、宗門子弟をどのように育成するか 赤堀 正明 結び:仏教教育の現状と課題をめぐって 仲澤浩祐 |
リポジトリ |
| 【第3号】 | |
|
〈論 文〉 高橋堯昭 「カニシカ仏陀コイン「掌中の珠」の意味するもの」 上田本昌 「身延期における日蓮聖人の如説修行」 〈史料紹介〉 寺尾英智 「日蓮『一代五時図』の身延山真蹟曽存本─京都本満寺所蔵の日乾筆真蹟臨写本について─」 望月真澄 「江戸の日蓮宗の年中行事 (二)─『武江年表』にみられる縁日・開帳・祈願を中心に─」 〈翻 訳〉 望月海慧 「アティーシャの『菩提道灯論細疏』和訳(1)」 〈英文論文〉 三輪是法 A Study of Difference of Gender in Nichiren's Concept |
リポジトリ |
| 【第4号】 | |
|
宮崎英修先生略年譜・主要著述論文目録 〈追悼文〉 得珠院日漸上人歎徳文 身延山学園理事長 藤井 教雄 弔辞 仲澤浩祐 宮崎英修先生を偲ぶ 浅井 円道 宮崎先生と私 望月 海淑 宮崎先生が関心をもたれた最終講義のメハサンダ遺跡 高橋 堯昭 宮崎英修先生の想い出 上田 本昌 宮崎先生との出会い 町田 是正 〈論 文〉 中山光勝 「明治四年・松山県浮穴、久米二郡農民騒擾裁判小考」 〈研究ノート〉 望月真澄 「江戸の日蓮宗の年中行事(三)」 |
リポジトリ |
| 【第5号】 四教授退職記念号 | |
|
巻頭言 学長 浅井圓道 高橋堯昭教授・望月海淑教授・町田是正教授・上田本昌教授 略歴・研究業績 〈最終講義〉 塔とサンガ─僧伽から仏塔重視・更に仏塔否定から法の重視へ─ 高橋堯昭 法華経と私 望月 海淑 歴史と文法 町田 是正 『観心本尊抄』の【本尊段】について 上田 本昌 〈論 文〉 岩田諦靜 「真諦訳『摂大乗論世親釈』における増広部分の検討─釈依止勝相品(所知依章)─」 望月真澄 「江戸城大奥女性の代参について─鼠山感応寺の事例を中心に─」 〈研究ノート〉 池上要靖 「原始仏教の福祉行動に関する原典研究ノート─増一阿含第四十について─」 〈資料紹介〉 中山光勝 「魘魅人条例の制定に関する一資料」 〈翻 訳〉 望月海慧 「ディーパンカラシュリージュニャーナの『菩提道灯論細疏』和訳(3)」 |
リポジトリ |
| 【第6号】 深山正光教授退職記念号 | |
|
巻頭言 学長 浅井圓道 深山正光教授 略歴・研究業績 〈最終講義〉 現代学校の役割を問う 深山 正光 〈論 文〉 浅井圓道 「日本天台法華仏教の成立とその特質」 望月真澄 「江戸城大奥「祈祷所」の機能と性格─江戸法養寺の事例を中心に─」 三輪是法 「日蓮遺文の物語性」 桑名貫正 「ハンセン病救済事業・身延深敬病院における十萬一厘講勧募活動について」 間宮啓壬 「日蓮における身延入山の意図と意義(承前)」 〈研究ノート〉 志田 利 「生涯学習と福祉教育─福祉教育研究普及校のとりくみ─」 〈資料紹介〉 中山光勝 「明治六年の火葬禁止に関する公文書」 本間裕史 「遺言と血脈─『宗祖御遷化記録』の遺言をめぐって─」 〈翻 訳〉 望月海慧 「ディーパンカラシュリージュニャーナの『菩提道灯論細疏』和訳(4)」 |
リポジトリ |
| 【第7号】 浅井圓道先生退職記念号 | |
|
浅井圓道先生 略歴・研究業績 〈最終講義〉 我が教学研究五十年 浅井圓道 〈論 文〉 岩田諦靜 「真諦訳『摂大乗論世親釈』における増広部分の検討 (二)─釈依止勝相品(所知依章)─」 〈研究ノート〉 志田 利 「在家信者の福祉実践─山城多三郎の金谷民生寮─」 〈資料紹介〉 中山光勝 「明治四年・伊賀農民騒擾裁判関係資料(二)」 望月真澄 「(翻刻)京都善正寺蔵「檀林録」」 〈翻 訳〉 望月海慧 「ディーパンカラシュリージュニャーナの『菩提道灯論細疏』和訳(5)」 |
リポジトリ |
| 【第8号】 立教開宗750年記念号 | |
|
〈論 文〉 上田本昌 「日蓮聖人の立教開宗をめぐって」 志田 利 「社会福祉における宗教の復権への一考察─小池政恩の実践に学ぶ─」 岩田諦靜 「真諦訳『摂大乗論世親釈』における増広部分の検討(四)─釈依止勝相品(所知依章)─」 高橋一公 「身延山大学における学生の意識(1)」 望月海淑 「如来滅後五五百歳始考」 〈翻 訳〉 望月海慧 「ディーパンカラシュリージュニャーナの『菩提道灯論細疏』和訳(6)」 |
リポジトリ |
| 【第9号】 岩田 諦静先生退職記念号 | |
|
岩田 諦静先生 略歴・研究業績 〈最終講義〉 九識説と日蓮宗 岩田 諦静 〈論 文〉 志田 利 「福祉から仏教に期待するもの」 野澤清美 「法華経「方便品」における仏像造像の材料について」 〈資料紹介〉 中山光勝 「乃木希典日記─明治八年─(一)」 〈翻 訳〉 望月海慧 「ディーパンカラシュリージュニャーナの『菩提道灯論細疏』和訳(7)」 |
リポジトリ |
| 【第10号】 志田 利先生退職記念号 | |
|
志田 利先生 略歴・研究業績 〈最終講義〉 私の仏教福祉論 志田 利 〈論 文〉 高橋堯昭 「兜跋毘沙門天像成立に見られる西方文化の包容と大乗思想の具像化」 高橋智恂 「建学の精神の具体化─『福祉』教育への導入に関する事例─」 望月海淑 「羅睺羅をめぐって」 〈史料紹介〉 寺尾英智 「勝浦市妙覚寺所蔵「上総国興津村広栄山妙覚寺継図写」」 望月真澄 「京都市善正寺所蔵「六山会合要抜書」」 〈翻 訳〉 望月海慧 「ラトナーカラシャーンティ『経集解説・宝明荘厳論』和訳(1)」 |
リポジトリ |
| 【第11号】 | |
|
〈論 文〉 志田 利 「宗教者の福祉実践─富士育児院創設者渡辺代吉─」 志田洋子 「仏教福祉学科への願望」 〈資料翻刻〉 中山光勝 「明治十一年・神奈川県下真土村農民騒擾事件関係裁判資料(一)」 〈翻 訳〉 望月海慧 「ラトナーカラシャーンティ『経集解説・宝明荘厳論』和訳(2)」 |
リポジトリ |
| 【第12号】 | |
|
〈論 文〉 岩田諦靜 「上総七里法華における元文法難と伊藤玄基隆敬の生涯」 福祉慈稔 「十世紀初までの日本各宗に於ける新羅仏教の影響について」 〈史料紹介〉 望月真澄 「山梨県南部町正行寺蔵「朝師記念録 全」」 〈新刊紹介〉 望月真澄著『法華信仰のかたち その祈りの文化史』(大法輪閣) 三輪是法 〈報 告〉 深山正光先生の遺稿『国際教育の研究』出版の経緯と意義 田沼朗 〈翻 訳〉 望月海慧 「ラトナーカラシャーンティ『経集解説・宝明荘厳論』和訳(3)」 望月海淑 「陳景富 編著『草堂寺』(修訂本)の私訳」 追悼文 中山光勝 |
リポジトリ |
| 【第13号】 | |
|
〈論 文〉 岩田諦靜 「真諦訳『摂大乗論世親釈』における増広部分の検討(五)─釈依止勝相品(所知依章)─」 吉田永正 「終末期医療におけるいのちのさとり」 森 和子 「生まれくる子ども、親、ドナーの福祉を配慮した家族支援─オーストラリアの提供型生殖補助医療の調査をもとに─」 望月海淑 「塔に関しての疑義」 〈史料紹介〉 望月真澄 「車返霊場関係資料」 〈翻 訳〉 望月海慧 「ラトナーカラシャーンティ『経集解説・宝明荘厳論』和訳(4)」 |
リポジトリ |
| 【第14号】 志田洋子先生退職記念号 | |
|
志田洋子先生 略歴・研究業績 〈最終講義〉 私の社会福祉実践をふりかえって 志田洋子 〈論 文〉 長又髙夫 「鎌倉幕府成立論」 望月海淑 「羅什訳妙法華経の二三の問題」 〈翻 訳〉 望月海慧 「ラトナーカラシャーンティ『経集解説・宝明荘厳論』和訳(5)」 |
リポジトリ |
| 【第15号】 | |
|
〈講 演〉 『信貴山縁起絵巻』にみる病と信仰 小山聡子 〈論 文〉 金 炳坤(慧鏡) 「紀国寺慧浄の『法華経纉述』考(1)─新発見の史料をもとに─」 椿 正美 「六朝訳経の文体に見られる双賓構造の特徴」 〈研究ノート〉 望月真澄 「幕末期日蓮伝記本に関する一考察─中村経年著『日蓮上人一代図会』における弟子・信徒・寺院に関わる記載事項を中心に─」 〈翻 訳〉 望月海慧 「ラトナーカラシャーンティ『経集解説・宝明荘厳論』和訳(6)」 |
リポジトリ |
| 【第16号】 宮川了篤先生退職記念号 | |
|
宮川了篤先生 略歴・研究業績 〈最終講義〉 日蓮宗修法史概説 宮川了篤 〈論 文〉 山田雄司 「怨霊への対処─早良親王の場合を中心として─」 桑名法晃 「本妙日臨律師の研究」 望月海慧 「Tãranãtha の dBu ma theg mchog第5章「五法と三性と縁起の決択」について 〈研究ノート〉 間宮啓壬 「日蓮遺文の文献学研究とその成果」 |
リポジトリ |
| 【第17号】 長澤市郎先生退職記念号 | |
|
長澤市郎先生 略歴・研究業績 〈最終講義〉 仏像修復の理論と実践 長澤市郎 〈論 文〉 金 炳坤(慧鏡) 「紀国寺慧浄の『法華経纉述』考(2)─韓国の現存本をもとに─」 楢木博之 「相談援助専門職の行う相談と身近な相談の違い─相談援助の価値と原則─」 伊東久実 「レッジョ・アプローチによるドキュメンテーションの実例検討」 |
リポジトリ |
| 【第18号】 | |
|
〈講 演〉 日蓮聖人と大震災─身延山大学公開講演会講演録─ 中尾 堯 〈論 文〉 南 宏信 「新羅義寂撰『無量寿経述記』の撰述年代考」 金 炳坤(慧鏡) 「六朝古逸『法華経疏』の同本離片に関する一考察」 望月海淑 「常不軽菩薩品を巡って」 |
リポジトリ |
| 【第19号】 | |
|
〈論 文〉 伊東久実 「学生による身延町子育て支援とその教育的効果」 望月海淑 「久遠ということ」 〈報 告〉 北村愛子・佐々木さち子 「高齢者の誤嚥予防対策」 〈翻 訳〉 片山由美 「コータン語『法華経綱要』の試訳」 望月海慧 「チベット語訳『妙法蓮華註』「五百弟子受記品」和訳」 |
リポジトリ |
| 【第20号】 山田英美先生退職記念号 | |
|
山田英美先生 略歴・研究業績 〈最終講義〉 「遊び」再考 山田英美 〈論 文〉 椿 正美 「『法華三部経』に見られる使令兼語式構文の意味構造」 金 炳坤・桑名法晃 「義寂釈義一撰『法華経論述記』の文献学的研究(2)」 〈資料翻刻〉 中山光勝 「明治二年・伊那県筑摩郡農民騒擾関係裁判資料(一)」 〈翻 訳〉 望月海慧 「チベット語訳『妙法蓮華註』「化城喩品」和訳」 〈追悼文〉 志田洋子先生の思い出 浜島典彦 『身延論叢』総目次(自創刊号至一九号) 金 炳坤 |
リポジトリ |
| 【第21号】 | |
|
〈追悼文〉 故中山勝光教授を悼んで 池上要靖 〈講 演〉 富士山の世界文化遺産登録─身延山大学公開講演会講演録─ 清雲俊元 〈論 文〉 椿 正美 「『妙法蓮華経』の譬喩表現に関する一考察」 〈研究ノート〉 Jill Emma STROTHMAN, Yukina IKEDA A Study of Two Types of Traditional Lao Paint 〈翻 刻〉 望月真澄 「翻刻 深見要言編著「蒙古退治旗曼荼羅記 全」」 |
リポジトリ |
| 【第22号】 | |
|
〈研究ノート〉 Jill STROTHMAN, Yukina IKEDA, Phimpha PHONGSAVATH 2015-2016 Lao PDR Traditional Cement Research 〈論文〉 椿正美「「法華七喩」の表示で用いられる当然・義務の助動詞」 中井本勝「吉蔵撰『法華論疏』の文献学的研究⑵」 〈講演〉 近代日本における政治と宗教 信教自由の確立をめぐる思想状況─身延山大学公開講演会講演録─ 西田毅 |
リポジトリ |
| 【第23号】 | |
|
〈講演〉 仏教民俗学の視点から葬送儀礼を考える─身延山大学公開講演会講演録─ 高見寛孝 〈論文〉 長又高夫「鎌倉北条氏列伝(三)北条時頼」 椿正美「「法華七喩」の表示で用いられる禁止否定の副詞」 望月海慧「チベット語訳『妙法蓮華註』「方便品」和訳(1)」 |
リポジトリ |
| 【第24号】浜島典彦先生退職記念号 | |
|
浜島典彦先生 略歴・研究業績 〈最終講義〉 私は身延山大学で考えた―過去に学び、未来に託す― 浜島典彦 〈講演〉 ブッダの母 摩耶夫人に学ぶこれからの子育て─身延山大学公開講演会講演録─ 益田晴代 〈研究余滴〉 槇殿伴子「ネパールにおけるフィールドワーク―ネパール大地震から3年―」 〈論文〉 三輪是法「姉崎正治と日蓮」 椿正美「『妙法蓮華経』に見られる“況”字構造の機能的分析」 望月海慧「チベット語訳『妙法蓮華註』「方便品」和訳(2)」 |
リポジトリ |
| 【第25号】特集 円弘と妙法蓮華経論子注 | |
|
〈論文〉 金天鶴「『法華経論子注』写本の流通と思想」 岡本一平「円弘撰『円弘師章』の逸文研究」 金炳坤「円弘撰『妙法蓮華経論子注』研究史概観 桑名法晃「本妙日臨における元政の影響―受戒の作法とその精神―」 楢木博之「専門研修Ⅰ 自己評価から見えた介護支援専門員のケアマネジメントにおける課題」 椿正美「『妙法蓮華経』に於ける被動文の成立条件」 〈論評〉 蓑輪顕量「金天鶴「『法華経論子注』写本の流通と思想について」のレスポンス」 〈講演〉 物語の中の仏教、仏教の中の物語 岡田文弘 |
リポジトリ |
| 【第26号】特集 身延山の文化財 | |
|
〈論文〉 中尾堯「日蓮聖人真蹟と初期の身延文庫」 有賀祥隆「身延山久遠寺蔵仏涅槃図について ─ あるいは釈迦の姿態 とくに右手の表現について-」 渡辺洋子・㓛刀悠「七面山敬慎院本社の前身建物と七面造について」 庵谷行亨「日蓮聖人教学における仏法の弘通(三) ─ 四依の菩薩を中心として-」 桑名法晃「深草瑞光寺所蔵『宗祖一代本尊鑑』(二)─ 『聖人御系図御書』を中心に ─ 」 金炳坤「利都法師撰『法華経義記』攷(3) ─ もう一つの同本離片について ─ 」 中井本勝「吉蔵撰『法華論疏』の文献学的研究(5)」 楢木博之「介護支援専門員のケアマネジメントプロセスにおける課題 ─ 2年間の自己評価から見えてきたこと ─ 」 |
リポジトリ |
| 【第27号】 | |
|
〈追悼文〉 故高橋堯昭教授・故望月海淑教授・故町田是正教授を悼んで 池上要靖 〈論文〉 庵谷行亨「日蓮聖人遺文における「開袥」の文字について」 岡田文弘「日蓮と食人」 桑名法晃「本妙日臨の「本化律」」 槇殿伴子「『マニ・カンブン』における観自在菩薩の「六字真言成就法」―ソンツェンガンポ王の伝統による「実践指南口伝」(dmar khrid zhal gyi gdams pa)(分科と試訳)―」 |
リポジトリ |
| 【第28号】 | |
|
〈追悼文〉 故上田本昌教授を悼んで 池上要靖 〈論文〉 庵谷行亨「日蓮聖人における「一大事の教え」―身延期を中心として(二)―」 桑名法晃「「佐渡始顕本尊」考」 岡田文弘「本門戒研究序説―伝・日蓮『本門戒体抄』を題材として―」 岡本一平「道策・道榮撰〈法華疏〉逸文と〈紀国寺法華文献群〉」 槇殿伴子「『マニ・カンブン』における如意宝珠観自在菩薩成就法―実践指南(dmar khrid):悲を蔵する空性・睡眠と夢の瑜伽・ 輪廻の過失に染まらぬ蓮・倶生(サハジャ)智・自心仏―」 〈史料紹介〉 海老沼真治「遠光寺文書「河東惣導師免許状」」 〈研究ノート〉 金炳坤「韓国仏教全書第十五冊所収高麗撰述天台法華章疏解題」 〈講演〉 普賢菩薩の勧発のあとで―持続する『法華経』― 岡田文弘 |
リポジトリ |
入会案内
入会の方のお申し込みは、随時受付中です。
入会申し込みにあたっては、
「身延山大学仏教学会会則」をお読みいただき、
以下の申し込み用紙に必要事項を記入して、申込書記載の宛先に身延山大学仏教学会までメールまたは郵便でお送り下さい。
身延山大学仏教学会入会申込書:
(Word版)/
(PDF版)